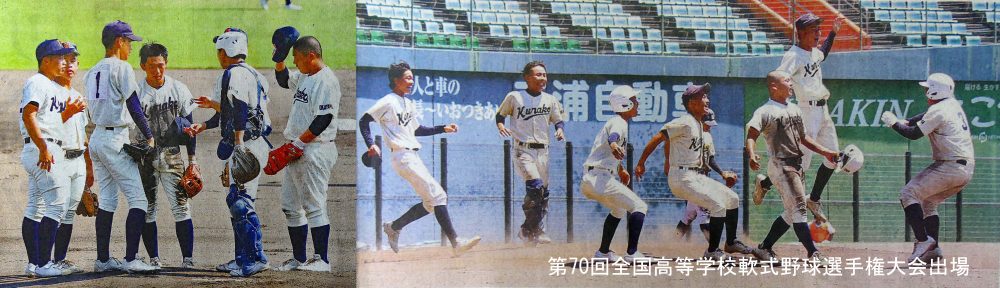白壁が美しい美観地区を見下ろす、鶴形山の阿智神社。この阿智神社は、倉敷総鎮守の宮である。10月の、秋季例大祭では阿智神社の御神幸は、美観地区から、倉工正門倉敷駅倉敷みらい公園周辺を巡回。この、御神幸を白装束に身を包んだ、倉敷工野球部員が地域貢献活動として、参加している。こうした中、倉敷工野球部に、半世紀以上に渡って続く伝統の、猛練習がある。その猛練習とは、この阿智神社の石段183段を、選手が全力で駆け上がる事。ランニングで、約10回駆け上がるのが、準備運動。その後は、石段、境内の坂道ダッシュと続く。
そして、個々に設定した、目標時間が達成できなければ、30回の腹筋運動が、待っている。毎年、選手たちは口を揃えて言う。
『正直言って、きついです。だけど、下半身が強くなり、これだけ走ったという、自信が生まれた。達成感もある。』この、阿智神社での、猛練習の事を、通称【山】と、呼ぶ。OBが「山は、二度とごめんだ。」と、口を揃える冬場の【山】。昭和50年春の選抜に出場した、コーチの神土秀樹は、「当時も、練習は山が、中心でした。」そして「ほぼ、毎日山を、走りました。野球の練習で、山が、一番きつい練習でしたね。山が、いやで退部する部員もいました。」「山は、慣れたか。」監督の、中山隆幸が選手に、問いかけた。その答えが、成果のバロメーターであろう。「技術より、全ての土台となる精神的な部分を育てたい。」と、中山。
OBの多くは、「山は、思い出したくない。」と、言う。それでも、少しづつ、「慣れました」と、答える選手が増えて行く事に、手応えを感じる事だろう。たゆまぬ努力は、結果になる。
地域貢献といえば、もう一つある。倉敷工野球部は、地域の清掃奉仕活動にも、汗を流している。「倉工甲子園に、行けよ。頑張って。」と、市民から、声を掛けられる機会もあり、地元の期待を、肌で感じながらの、奉仕活動である。この奉仕活動は、以前からあったのだが、中山が、監督に就任してから「もっと、地域から愛されるチームに、なろう。」と、範囲を拡大。週末の練習後、部員たちは、ユニホームのまま、倉敷駅から、倉敷市営球場まで足を、伸ばす。選手たちは、道端の、たばこの吸い殻や、用水路に浮かぶ空き缶を、火ばさみで、ビニール袋に手際よく回収して歩く。倉工グランドに住む、主婦からは、「礼儀正しく、清掃以外の時も、会うと必ず挨拶してくれて、気持ちがいい。ぜひ、甲子園に行ってほしい。」と、エール。選手は「感謝してもらうと、本当に力が出る。地元のためにも、絶対に甲子園に、行く。」と、意気込む。中山の、意図は『甲子園出場』だけではなかった。【地元から、愛されるチームになろう。】が、そこに、あった。
つづく 随時掲載
お願い
本文に迫力を持たせるため、敬称は略させて頂きます事をご了承下さい
参考
山陽新聞
毎日新聞
(当時の、新聞記事を参考にして、一部を引用しています)
協力
小山 稔氏「元倉敷工業高校野球部コーチ」
神土秀樹氏「元倉敷工業高校野球部コーチ」
和泉利典氏「元倉敷工業高校野球部監督」
中山隆幸氏「前倉敷工業高校野球部部長監督」